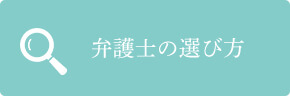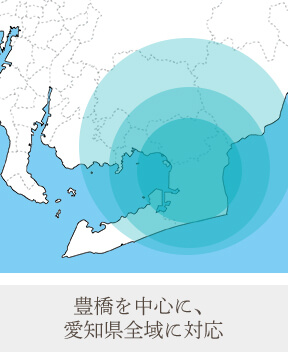退職代行サービスとは?なぜ非弁行為と言われるのか弁護士が解説
1 はじめに
退職代行という言葉を聞くことがあります。
従業員が自ら勤務先に対して退職の申し入れをするのではなく、退職しようとする従業員に変わって、勤務先の企業へ退職の意思を伝えたりするサービスを退職代行といいます。
従業員の方は、弁護士を依頼して、勤務先に対し、退職の申し入れをすることができます。退職にあたり、有給休暇の消化、残業代の請求、退職金の請求、ハラスメントに対する慰謝料などの法的な問題が生じても、弁護士であれば、代理人として、勤務先と交渉をすることができます。
それでは、弁護士ではない民間企業が、退職代行業務をすることについて、問題はないのでしょうか。
2 退職の申し入れに関する民法の規定
(1)民法の規定
民法627条1項は、
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
旨を規定しています。
雇用期間のない正社員の方の場合(多くの正社員は、雇用期間がないと思います)、正社員の側からの解約申し入れをした場合、解約の申し入れの日から2週間で雇用契約が終了します。
勤務先の同意は、必要とされていません。従業員の方は、民法の規定にしたがって、退職の申し入れをすることができます。
3 非弁行為(弁護士法72条)
弁護士法は、弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件・・・その他一般の法律事務に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」旨規定しています。
そうすると、退職しようとする従業員の方が、弁護士、弁護士法人でない民間企業に、報酬を支払って、退職の意思を伝えるにあたり、例えば、残業代の請求について、交渉をしたりすると、弁護士法違反の問題が生じる可能性があります。
退職にあたり、有給休暇の消化、残業代の請求、退職金の請求、在職中のハラスメントに対する慰謝料など、様々な法律問題が生じる場合があります。
法律問題について、弁護士等の専門家が関与しない場合には、退職しようとする従業員の方が、法律的な問題について、正当な法律的な保護を受けることができなくなる可能性もありますので、注意が必要だと思います。
4 従業員の立場から
従業員の立場からすると、退職にあたり、単に退職の意思を伝えるだけで良いか、それ以外に、法律的な問題がないか、確認が必要だと思います。
法律的な問題が生じる可能性があるのであれば、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。
5 勤務先の会社の立場から
勤務先の会社としては、従業員から、退職の意思表示がなされた場合、民法、弁護士法といった法律の規定を踏まえたうえで、従業員の退職について、対処することが良いと思います。退職について、法律上、勤務先の会社の同意は、必要とされていません。従業員の退職の意思を尊重し、法律の規定にしたがって対応する必要があると考えられます
次に、勤務先の会社としては、退職の意思表示を誰が伝えてきたかに応じて、対応が変わってくると思います。
①弁護士
弁護士は、従業員の代理人という立場になります。
弁護士は、依頼者から委任を受ければ、法律問題について、代理人として、交渉する権限があり、訴訟、労働審判の提起をすることができます。
弁護士が従業員の代理人に就任した場合には、勤務先の会社の側も弁護士に相談をされてはいかがでしょうか。
②労働組合
労働組合が従業員に代わって、退職条件について交渉をしてくる場合があります。ここでは、詳細な説明は省略します。
③民間企業
民間企業が退職代行を行うこと自体は、違法ではないと考えられます。
もっとも、既に述べたとおり、弁護士法の規定があるため、退職にあたり、民間企業が、依頼を受けた従業員の残業代の請求、退職金の請求などをしてきた場合には、非弁行為として違法になる可能性があります。
勤務先の会社としては、民間企業には、従業員の退職に関し、取り扱うことができる業務に制約があることを理解したうえで、対応する必要があると思います。
勤務先の会社としては、従業員自ら退職の申し入れをすることなく、退職代行を利用して退職の意思表示をしてきたことについて、会社の労働環境、従前の会社と当該従業員の間の人間関係などについて、問題がなかったか、今一度、振り返ってはいかがでしょうか。そのうえで、改善点が見つかれば、よりよい労働環境を整備するため改善をしていく必要があると思います。
6 まとめ
従業員の方は、法律の規定にしたがって、退職の申し入れをすることができます。
もっとも、従業員の方が、退職を申し入れると、勤務先との間で混乱が予想される場合もあり、そのような場合、弁護士等を通じて、退職の意思を勤務先の会社に伝えることもあると思います。
従業員の方も、勤務先の会社も、双方とも、法律の規定を踏まえた上で、冷静で適正な対応をすることが必要だと思います。
執筆弁護士紹介

-
寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。
最新の投稿
 新着情報11月 12, 2025退職代行サービスとは?なぜ非弁行為と言われるのか弁護士が解説
新着情報11月 12, 2025退職代行サービスとは?なぜ非弁行為と言われるのか弁護士が解説 弁護士コラム10月 1, 2025シャボン玉石けん株式会社代表取締役森田隼人氏の講演を聴いてきました
弁護士コラム10月 1, 2025シャボン玉石けん株式会社代表取締役森田隼人氏の講演を聴いてきました Uncategorized6月 20, 2025戸籍の氏名に振り仮名が記載される制度が始まります
Uncategorized6月 20, 2025戸籍の氏名に振り仮名が記載される制度が始まります 弁護士コラム4月 15, 2025顧問先の企業様において、セクハラ、パワハラ研修をさせていただきました
弁護士コラム4月 15, 2025顧問先の企業様において、セクハラ、パワハラ研修をさせていただきました